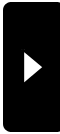2006年05月29日
特定外来生物ネタその4
バスのベストシーズンを迎え、釣り人も活発になってきたが、
同時に、外来魚を駆除する団体の行動も活発になってきた。
宮城県栗原市の伊豆沼・内沼では、バスの産卵習性を利用
した駆除が本格的に始まった。
県伊豆沼・内沼環境保全財団の職員やボランティアが4月
下旬から、園芸用トレーに小石を敷いた50センチ四方の
人工産卵床を岸沿いに約400カ所設置し、3日おきにチェック
しているそうです。そして産卵を確認すると刺し網を仕掛け、
親魚と卵を根こそぎ捕獲するということだ。この方法は成果を
あげるものとして全国へその方法をマニュアル化し、なんと
DVDの配布までするという力のいれようです。
また、京都の保津川では、以前にもお伝えしたように、「全国
一斉ブラックバス防除ウイーク」(5月22日-28日)に合わせて、
保津川漁業協同組合や市内のNPO法人(特定非営利活動法人)
などの協力で行われた。
個人的に気になるのは、この駆除に外来魚の知識も持たない
子供達を巻き込んで、一方的にバスやギルは、小魚を捕食する
から悪いでしょ!と頭ごなしに決め付けさせるというやり方が
腹立つ!
また、同じような子供を使った駆除は、大阪・淀川でも行われて
おり、まるで釣りの楽しさと教えるかのように偽って、バスやギル
を釣らせる釣り大会を行っているのだ。その大会名も「外来魚駆
除釣り大会」。
いずれも詳細や経緯は把握していないが、もともとその水域に
生息していたタナゴやモツゴなど数が外来魚だけで少なくなった
ということに決め付けてほしくないですね。確かに1つの要因とし
てはあるかもしれないが、汚染による水質悪化などの要因や、
それこそ、外来魚と在来種のゾーニングみたいなことも含めて
問題を捉えてほしいなぁと思います。
だって、在来種の中には、小魚を食べるウグイやオヤニラミ
のような魚種もいるわけで、小魚減少の要因がバス・ギルのみ
に特定されるのもねぇ~。
(バス・ギルの絶対数が多いことは認めるが・・・)
5年先、10年先の日本のバスフィッシングってどうなっちゃうん
だろう?
同時に、外来魚を駆除する団体の行動も活発になってきた。
宮城県栗原市の伊豆沼・内沼では、バスの産卵習性を利用
した駆除が本格的に始まった。
県伊豆沼・内沼環境保全財団の職員やボランティアが4月
下旬から、園芸用トレーに小石を敷いた50センチ四方の
人工産卵床を岸沿いに約400カ所設置し、3日おきにチェック
しているそうです。そして産卵を確認すると刺し網を仕掛け、
親魚と卵を根こそぎ捕獲するということだ。この方法は成果を
あげるものとして全国へその方法をマニュアル化し、なんと
DVDの配布までするという力のいれようです。
また、京都の保津川では、以前にもお伝えしたように、「全国
一斉ブラックバス防除ウイーク」(5月22日-28日)に合わせて、
保津川漁業協同組合や市内のNPO法人(特定非営利活動法人)
などの協力で行われた。
個人的に気になるのは、この駆除に外来魚の知識も持たない
子供達を巻き込んで、一方的にバスやギルは、小魚を捕食する
から悪いでしょ!と頭ごなしに決め付けさせるというやり方が
腹立つ!

また、同じような子供を使った駆除は、大阪・淀川でも行われて
おり、まるで釣りの楽しさと教えるかのように偽って、バスやギル
を釣らせる釣り大会を行っているのだ。その大会名も「外来魚駆
除釣り大会」。
いずれも詳細や経緯は把握していないが、もともとその水域に
生息していたタナゴやモツゴなど数が外来魚だけで少なくなった
ということに決め付けてほしくないですね。確かに1つの要因とし
てはあるかもしれないが、汚染による水質悪化などの要因や、
それこそ、外来魚と在来種のゾーニングみたいなことも含めて
問題を捉えてほしいなぁと思います。
だって、在来種の中には、小魚を食べるウグイやオヤニラミ
のような魚種もいるわけで、小魚減少の要因がバス・ギルのみ
に特定されるのもねぇ~。
(バス・ギルの絶対数が多いことは認めるが・・・)
5年先、10年先の日本のバスフィッシングってどうなっちゃうん
だろう?
Posted by 会長 at 17:03│Comments(0)
│特定外来生物